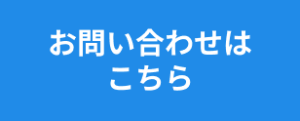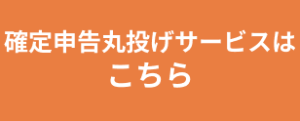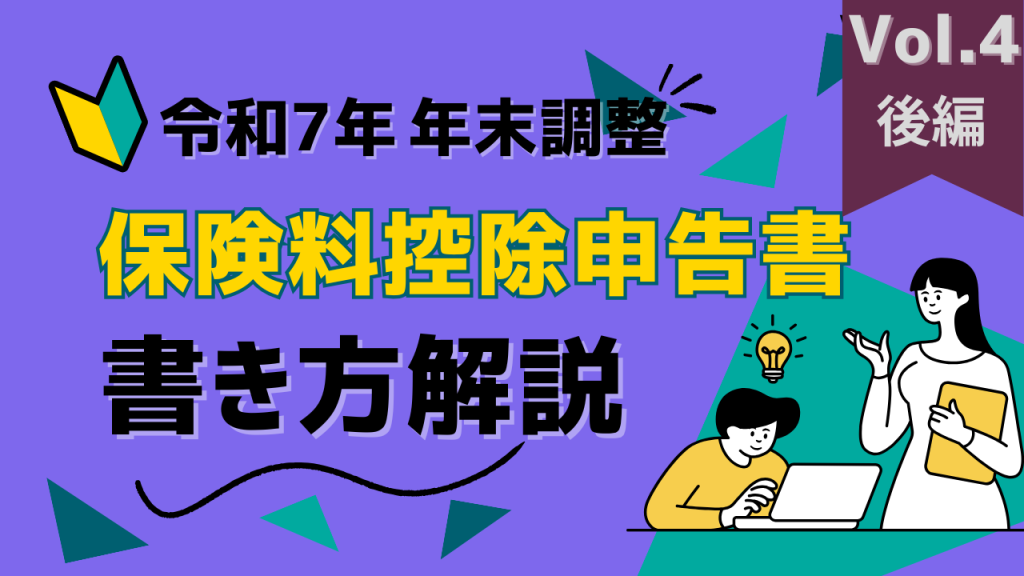目次
医療費控除額の計算式
「医療費控除」について、何が対象で、何が対象外になるのか具体的な事例を用いてご紹介いたします。
そもそも「医療費控除」とは、多額の医療費を支払った場合、確定申告を行うことによって所得控除が受けられる制度です。
よく「10万円以上の医療費を支払うと医療費控除が受けられる」と言われますが、
正確には次の算式で医療費控除を計算します。
(支払った医療費-保険金等で補填される金額)-10万円(※)
=医療費控除額(最高200万円)
(※)総所得金額が200万円未満の方は、その5%相当額。
よって、「10万円」か「総所得金額の5%」のいずれか金額の少ない方より、多く医療費を支払っていた場合に、医療費控除を受けられることになります。
ただし、医療保険などにより、医療費の一部が保険金で補填される場合は医療費控除額が変わってくるので注意が必要です。
これって医療費控除の対象?具体例をご紹介
ここからは、具体的なケースをご紹介いたします。
状況によって、控除の対象となるかどうかは異なりますので、ご自身のケースと照らし合わせて、ぜひ確認してみてください。
Q1.新型コロナウイルス感染症のPCR検査費用は、医療費控除の対象になりますか?
A1.新型コロナウイルス感染症に感染している疑いのある方に対して行うPCR検査など、医師等の判断により受けたPCR検査の検査費用は、医療費控除の対象となります。
ただし、自己の判断により受けたPCR検査の検査費用は、疾病の治療を伴うものではないので、医療費控除の対象とはなりません。
- ポイント
医療費控除を受ける際の重要な証拠となりますので、医師から検査の必要性を告げられた際の領収書・カルテ等を保管しておきましょう。
Q2.マッサージ代・はり代は医療費控除の対象になりますか?
A2.治療のためのあん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師などの施術の対価として支払うマッサージ代・はり代は、原則として医療費控除の対象となります。
ただし、健康維持のためのマッサージ代・はり代は医療費控除の対象とはなりません。
- ポイント
医療費控除を受ける際の重要な証拠となりますので、治療に関わった領収書を保管しておきましょう。
Q3.通院のための公共交通機関の利用料金は医療費控除の対象になりますか?
A3.医師等による診療等を受けるための通院費は、医師等による診療等を受けるために直接必要なものなので、医療費控除の対象になります。
ただし、タクシーの利用料金については、そのすべての金額が医療費控除の対象となるわけではありませんが、
電車、バス等の公共交通機関が利用ができない場合のタクシー利用料金は、その全額が医療費控除の対象となります。
- ポイント
公共交通機関でも、タクシー利用でも「通院日、交通機関名、利用区間、料金」などを記録しておきましょう。
Q4.診断書などの作成に係る文書料は医療費控除の対象になりますか?
A4.診断書などの作成に係る文書料については、医師等の診療や治療の対価に該当しないことが一般的であるため、医療費控除の対象にならないと考えられます。
ただし、医療費控除の対象に含まれる文書料もありますので、お気軽にご相談ください。
以上のように、医師等の治療の対価や、医師等の判断による検査の費用、それに伴う交通費などが医療費控除の対象となります。
医療費控除は年末調整で申告することができず、確定申告を行う必要があるので忘れずに申告しましょう。